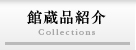お知らせ
2019.10.08
お詫びと訂正 区報ぶんきょう記載間違いについて
区報ぶんきょう令和元年10月10日号にて、日程の記載間違いがありましたのでご報告いたします。
記
<訂正内容>
(誤)特別展「永井荷風と鴎外」を開催中です。
(正)特別展「永井荷風と鴎外」を10月12日(土)から開催中です。
区報ぶんきょう令和元年10月10日号をご覧になった皆様には、お詫び申し上げます。
10月7日(月)から10月11(金)まで、展示替えのため全館休館いたします。
10月12日(土)からは、特別展「永井荷風と鷗外」を開催いたします。ぜひ、お立ち寄りください。
森鴎外記念館NEWS28号をアップしました!
今号では、全国の個人顕彰文学館との連携を図るため、ゆるやかにシリーズ化しているコラムで、いわき市立草野心平記念文学館様にご執筆いただきました!また、現在販売中の書簡集2を監修された、大妻女子大学教授・須田喜代次氏より編集を終えての感想を掲載させていただきました。
本誌は館内配布の他、区内施設や都内文学館の一部などでも配布いたします。
また、こちらでもご覧いただけます。是非ご覧ください!
明日、9月24日(火)は第4火曜日のため全館休館です。
9月25日(水)より通常通り開館いたします。
開催中の「文学とビール ―鴎外と味わう麦酒の話」を引き続きお楽しみください。